
創刊号
〜コトバへの挑戦〜
- 接近 清水かおり
- 「言葉への挑戦」という命題はそれぞれの中でどう消化されたのだろう。一句一句読むごとに、模索した過程が見えることを今回は楽しんだ。
言葉を所蔵する吉澤久良
草奔のみみはな未明の泥寡黙
原稿を書きながらこの句に同化していた。「草奔のみみはな」が心にあるナルシスな部分を増幅させている。この句のように、吉澤久良は言葉の振り幅を利用して十七文字を最大限活かす書き方をする。言葉に内在するものをしっかりと意識させ一度沈潜させた上で意図する場所へ引き上げていくという書き方だ。まるで、意味に意味を重ねることによって句意が無限を成し得るということの飽くなき証明をしているかのようである。
今回、「破」「転」「容」は読者を導く標であるが、バックストロークやふらすこてんの作品にも吉澤の心中にはいつも主題や命題が置かれていると感じてきた。作品が流れを形成しているからだ。こういう書き方は一句目から最後の句まで読み手の熱を持続させるので、波長が合うと容易に逃れられない魅力になる。ただ今回は、読みの途中で無意識に句と題を行き来するというごく些細な作業が、句の勢いを削いでしまう不安を思った。
吽形のプロメテウス水ぶくれの月
紺碧を琥珀の王が攻めてくる
末黒野にピンクの杭がある 痒い
質量、硬度、光度、色覚、それぞれを二種対峙させると生じる緊迫が「破」の心理を誘ってくる。神話的残像、事後の不安、を読者は想像し、そこに投影されているものは攻防の痕の景色とわずかな痒みのみなのだと知らされる。「痒い」が7句すべてにかかるところが吉澤の意図する核か。
擦過傷 花ざかりの森 忘れ水
ゼラチンの鳥 まくれる顔面 神の抜け毛
神聖文字から折れた智恵の輪
言葉のコラージュから現われるのは、継続していく生の様子である。転がる立方体に描かれた絵のように濃淡を見せながら、生が死と同じように受身なのだと教え、「忘れ水」「神の抜け毛」という結果が用意されているところに川柳性と普遍性を置いている。
吉澤の作品は普段使いしない言葉の多用のせいで一読では近寄りがたいものを感じさせることがある。何故そう感じるのか。それは私達と言葉の間に訓練という関係があるからではないだろうか。言葉に反応して物や事を認識するということを積み重ねている以上、普段使いしない言葉との出合いはやはり一拍の間を生んでしまうのだ。そのためこれらの句のイメージの授受とそれにかかる時間は読み手の訓練に委ねられているといえる。
この意味で川柳の環境は作家にとって大きな要素になり得る。解り合える環境で作家は更に冒険ができるし、句が空回りすることもないので居心地がよい。しかし、環境に甘えてしまう危うさの認識は個々でしっかりとしておかねばならない。
デボン紀の海につながる循環器
枕木に撒く群青の言霊
温帯のビニールホース所在なく
流木へ寄りそう銅の魚たちよ
詩性に傾斜した言葉がロマンを漂わせる。それが少し色濃く出ているのが今回の20句の特徴かと思う。「循環器」「温帯」の許容と「枕木」「流木」の変容、それらの時間的経過に我々の外界と内界の出来事が大きく包み込まれている。
少し乱暴だが、句を逆順に読んで吉澤の意図に逆行してみた。すると、あきらかにエネルギー配分の違いが見え、「魚たちよ」と語りかける句は後方に位置しなければならないことがわかる。句に流れを創ることに細心の注意を払ってこれらは構成されているのだ。
難解句といわれる句は言葉と言葉の間にある空間を読むことが要求されるが、言葉の展開が突飛すぎると奇異な感覚が先に立ち、句の真意や飛躍の空間に辿り着けないこともある。しかし、吉澤の空間には難解性はあっても異質なものは紛れ込まない。これは偶発的に生まれる句意を吉澤が想定していないからではないだろうか。そしてこの20句に関して言えば全体イメージを受け取りやすく構成されているように思える。つまりこれから吉澤がやろうとしていることのプロローグとして提出されていると言える。
かげろうたぎる黄濁の川 沐浴
蝶番のように「破」「転」「容」をつないですべてのバランスを決定した最後の句は美しく強い。こういう締め方が吉澤の本質だと理解している。
兵頭全郎のアルカイックスマイル
目ニハ青葉ハハと赤子の口動く
恋文なら柿の葉寿司の具になれる
たばこ消す夕日ぽろんと無くなって
兵頭全郎の作品に対する先入観はいつ生まれたのか。自他の非在はもとより共感や納得の無意味化のような句、知恵の輪の玩具のような関係が兵頭と川柳の間にあって私達はそれを見ているのだと思っていた。
「こと・の・は」は「leaf」を材料に使い、意外に体温の高い句という印象を持った。生活感がモチーフにされているせいだろうがこれは「unreal」と題された仕掛けのひとつにすぎない。兵頭が非在や無意味化を書いている時の内的エネルギーは私達と変わらないはずであるから、モチーフによってこういう一面(体温)が出てくるのは当然ともいえる。
かたことかたこと山並みの寝姿
坂に沿う模様にひとつご相談
身近な周囲の在りようが書かれている。拒否をしているわけではないが特に近寄るわけでもない、無機質でもなく揶揄でもなく、この所在なさが兵頭の持ち味ともいえる。ここでは「ひとつご相談」だけが妙に能動的なのが面白い。ここが社会との窓口ですよと案内されているようだ。
横線二本 オーロラのなる木を抜かん
楕円の影 いざ銭湯のおとなりさん
傾く筒 ひきだしサイズのドラえもん
語尾が「ん」で揃えられ、耳に近く目には遠い。ふらすこてん5号のル止め10句や「けいよう」の語尾の揃え方など、こういう仕掛けが兵頭の好むところらしい。「遠近」3句は、横線二本、楕円の影、筒の中の空気が仮想へ反転するときのそれぞれのリアルな距離を考えることが楽しかった。私達が句を読むときの視点は読んでいる主体か書いている主体が大方だが、どちらも関係ない位置に句を置くことにより、川柳と作者の距離、あるいは川柳と社会の関係を新しい方向で更新したいという欲求を感じさせている。
カリテス÷3=隣の隣の実
勤めあげまして明日のペレロポン
カドモスの土産を高く高く積む
兵頭の句はどれを取り出しても同じウエイトで書かれている。抑揚がないのだ。そのためかそれぞれの題はじゃまにならない。むしろ題も句も並列な感がある。
ギリシャ神話を知っていればこれらが上手く仕上げられた句だとわかる。物語を一句に纏めてここまで簡潔に消化出来るのか、こんな楽しみ方をするのかと感心した。そして、ここではそれが解ればいいのだと思った。何か思い入れがあるわけではないのだから兵頭にとってはこれがトロイア戦記でも日本書紀でも別にかまわないのだ。
私達は川柳を書くという行為を自己表出などさまざまな言葉に置き換えるが、兵頭の20句には、川柳は川柳という名の書き物としての認識であればいいというメッセージが置いてあるだけだ。そして、架空の日常からリアルな非日常へ軽々と場面を移しながら、ここで川柳の何が進行しているかを考えさせるのである。
兵頭の句にある“決まりごと”の連作は技法として私達を楽しませる一方で川柳の進化させるべき部分を提示し実践しようとしている。そこには現代川柳への極めてリアリスティックな批判が底流しているように思う。
畑美樹と草原に立つ
夕暮れの大腿骨のありがとう
マザーAからマザーBへ届ける耳
かたまりを配る大きな声だして
水平に運ぶ耳たぶの厚さ
身体の一部を使うことが多い畑の句は不思議なことにどんなに体内化しても実際の生身は排除されていく。それはこれらの言葉が畑の世界観に繋がっていると感じさせるからだ。拡散するかと思える空気が身体的言葉を通過することによって鍛えられた視点へと収斂されていく。私達はそこに世界のなんらかの構造が確かに映し出されていると感じながらそれを明確に論ずることができない。結果として畑の句が読者にはものすごく近く感じたり果てしなく遠く感じたりする。それでも読者は一様に作品が差し出しているしなやかなものを受け入れるのである。マザーABという小社会のグレーゾーン、かたまりという時間表象と閉塞、そして耳たぶの厚さになった史実や過去が運ばれて行く先、など平易な言葉で具象化された畑の思考を体感する格好になる。
見開きを縦に流れていくアジア
国家予算で桃を剥いている
舌先に触れているのは鯨の瞳
「アジア」「国家」が「流れて」「剥いて」いる本当の理由が個人の周囲でどこまでもずれていく。関心を世界の不条理に向ける作品は現実把握がしっかりしていないと書けない。畑の言葉選びには川柳が社会を取り扱うときに見られるメディア的論調がまったくない。それは畑が現実を社会のレンズではなく自身の目で確認しているからだ。溢れる情報の渦の中でその言葉に流されずに社会川柳を書くひとつの方向が示されているように思う。
筋肉を動かすように秋立ちぬ
ささやきながら蝶の背を押す
肉体を盾にほろほろ鳥眠る
川柳に書かれる「思考」は「思い」と同じように主観的でも句になったときの咀嚼時間に違いがある。「思い」に感情が加味されると更に早い段階で読者に答えとして伝わる。畑の句に情動的な言葉は見当たらない。が、句の多くに含まれる動詞のせいか思いがしきりに思考と交差している。
ありがとうと言う骨のかたち BS10号
夕暮れの大腿骨のありがとう Leaf
美しい素足を抱いているカラス BS12号
懸命に足をのばしてカラスになる Leaf
これらの句には4年の時間経過がある。実作をしていると自分と言葉の相性みたいなものを漠然と感じることがあるが、畑も例外ではないようだ。そこで大切になるのは句から句への上昇感だ。ありがとうという骨、素足を抱いているカラス、は一個体を描いて鮮やかであった。しかし今回の近似した句語からその個体へ私達が向かうことはない。夕暮れの大腿骨も後者のカラスも社会認識の描写として据えられるからだ。そこには確実に思考の質が作用している。私達の一句は常に未完成である。言葉との相性に凭れることなく自己模倣というジレンマに陥る危うさを越えて言葉への拘りを持ち続けることは、やがて作家一人一人の肉付けとなり作品が痩せることはないのだと思わせてくれる。
猫の腹動く四万十川指して
自分に接する外側の世界をひっくるめて自分の内側に保存するような感覚がある。「四万十」という地名に反応する思いがどこへ繋がってゆくか共に考えようと誰もが思う。畑の作品の言葉と身体との接続部分に出現する景がそう思わせているのだ。
(互評部分のみ抜粋。続きは本誌をご覧ください。)
戻る|
目次|
次へ
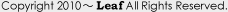
![]()
