
創刊号
〜コトバへの挑戦〜
- こんこん。 畑美樹
- 〈こんこん〉としている。漢字を当てはめるなら、〈懇懇〉、あるいは泉が湧き出でる〈滾滾〉も当てられるかもしれない。記号としての言葉への希求がとても強いのだ。その希求が止められず、止められない立ち位置から、句を成立させていく。
【破】から見てみよう。
熟慮を意味するという古代ギリシャの神が、口をしっかと結んで立っている。
吽形のプロメテウス水ぶくれの月
プロメテウスが見つめる先の月は水ぶくれであるという。水、すなわち生命の根源を喚起させるものでぶくぶくにふくれている月。本来、神々しい存在であってほしいはずの月が、神らしからぬ俗っぽさに浸っていることを嘆いているかのようだ。
プロメテウスの目線を吉澤本人の目線と見たらどうだろう。もちろん神ではない自分。その対極にある生そのものである自分の生臭さが、浮き上がってきた。俗っぽさをこそ、生臭さをこそ、と神の姿を借りて吉澤はつぶやいているのかもしれない。
末黒野にピンクの杭がある 痒い
天空から末黒野を見下ろすプロメテウスは、その風景に似合わないピンクの一点を見つける。しばらくして、杭であることを認め、「痒い」と一言。吽形の口元を緩ませたのは、人間の手による小さなピンクの点だった。
中原中也の歌集に『末黒野』がある。また、中也と聞けばすぐに思い出すのは「汚れちまった悲しみに」のフレーズだろう。「汚れちまった悲しみに なすところもなく日は暮れる」(中原中也 『汚れちまった悲しみに』より)。それらもまた、私たちの生の生臭さを懇懇と押し出している。
【転】には、一転して、その生臭い人間が、高貴なものとして、珍重すべきとしているものが登場してくる。
繭の疵 接着する指 ガラスの象
繭が作るシルクは古来から高貴な象徴。ガラスでできた象も、どこか神話の国の高貴さを思わせる。接着する指は、神に捧げる拝礼の一場面か。
神から人間へ投げられる視線から、今度は人間の側から神への視線へと、その位置を変えたのだろう。
囮小屋にて輪廻転生
囮としてこの世に差し出され続ける人間。この世は所詮囮小屋であると言う。そしてそこで輪廻転生は無限に続くと言う。そしてその小屋の中に、繭もガラスの象もある。
【破】に見える生の生臭さは、ここで生の愉しさに変化した。
さて、【容】では、生はどのように押し出されるだろうか。
デボン紀の海につながる循環器
生命の源は海、と言われる。その海と、今右手を当てている自分の心臓とがつながっていることを、静かに思う吉澤。生の生臭さの対極である神の視線、そして、所詮囮であるから愉しむよ、という神への視線を示し、【容】でそのふたつの視線は合体して、今この時の生を受け入れている。今、この瞬間息をしている、この今を。
かげろうたぎる黄濁の川 沐浴
生と死が共に在るガンジスの朝。生死がともに全てを受け容れる風景がそこにある。神は、死ぬことができない哀しさを抱え、人間は生と死の両方を感じ、愉しむことを与えられたのだ。
【破】、【転】、【容】それぞれの初句の初語と、最後の句の座語をつなげてみた。少し乱暴な言葉の扱い、お許しを。
吽形の 痒い
擦過傷 転生
デボン紀の 沐浴
口を結んで痒がる神の、そこはかとなき可愛らしさ。擦過傷まみれでも、転生し続ける人間の哀しき生命力。デボン紀の海で、ゆったりと沐浴をするアンモナイト。いささか遊びが過ぎるかもしれないが、吉澤の中にある生への希求の深さ、強さの全てが、句に注がれているのだと改めて思った。言葉という記号と川柳の形を得て、吉澤は生への問いかけを、始めたのかもしれない。
一連の作品には「架空の痛覚」というタイトルがつけられている。ギリシャの神プロメテウスも、プロメテウスが意味するという熟慮という行為も、そして、デボン紀のものたちも、もしかしたら全て架空で、痛覚だけが記憶として今、この現代に存在しているのかもしれない。
言葉への希求は、時に、架空の痛覚に出会う作業の連続なのだ。
戻る|
目次|
次へ
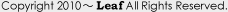
![]()
